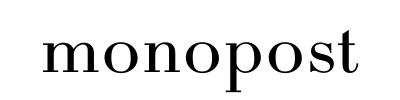Vol.3 民主主義 X 教育現場での体験
読者の皆さま、こんにちは!ドイツ在住ほぼ在宅フリーランスの高橋萌です。
「ヨーロッパの最先端事例は?」「Z世代のライフスタイルの変化は?」「〇〇業界のトレンドをリサーチせよ
!」と、様々なお題(ご依頼)に応えるべくマーケットの動向に目を光らせている筆者が、
「これは日本でも応用できそう!?」「日本人の琴線にも触れそうなコンセプト!!」「これは今、私が欲しい
……」と感じる、ドイツおよびヨーロッパのトレンドやライフスタイルの変化についてご紹介していきたいと思
います。
今回のテーマは、民主主義とどう向き合うかというお話です。
戦後80周年という節目を迎えた2025年、世界情勢が大きく変化する中で、ドイツでも日本でも国政選挙が行
われ、それぞれの社会が向かう方向に注目が集まっています。
戦後80年、民主主義を「鍛える」ドイツ
実際、私のところにも主権者教育や戦後の歴史教育をテーマに、日本からドイツへ視察や取材のお問い合わ
せがあり、年始からドイツの教育機関や青少年センター、歴史資料館などを訪問してきました。
投票行動には、その国の「民主主義との距離感」が表れると言いますが、右傾化する欧州にあって、ドイツも
例外ではなく、今年2月に行われた連邦議会選挙では極右政党AfD(ドイツのための選択肢)が大きく躍進し
ました。一方で、投票率は82.5%と、1990年の東西ドイツ統一以来、最高水準を記録しています。
投票率の低下が危惧される日本と、8割を超えるドイツ。主権者としてのあり方に、若い世代だけでなく、幅広
い世代が向き合う必要があるように思います。
皆さんは、政治や選挙、民主主義についてどのように学んだ経験がありますか?多くの人は、社会や公民の
授業の単元の一つとして、学校で先生から教わった記憶をお持ちかもしれませんね。
ドイツでは、学校教育における「政治教育」が「社会」や「歴史」と同等に必修科目として位置づけられていま
す。
ドイツの学校の授業を視察した際、特に印象的だったのが、教師が教科書をベースに知識を教えるのではな
く、生徒たちがリサーチしたことを発表したり、議論したり、その生徒たちの声が授業の中心にあったことです
。それぞれの意見や立場の違いを経験するプロセスが重視され、教師は議論を手助けするために知識や経
験を共有していました。
200万人の生徒が参加する本格的な模擬選挙
(Photo: Megumi Takahashi)
特に、学校単位で参加できる模擬選挙「ジュニア選挙(Juniorwahl)」の直前には、実際の選挙活動と並行
して、地域の候補者たちが学校に招かれて、生徒たちと対話し、各政党の公約について生徒が積極的に質
問できる機会も設けられます。
選挙権を持つ前の18歳以下の生徒が参加する、この本格的な「模擬選挙」は政治教育センターなどの支援
を受けて、実物とそっくりの投票用紙や選挙の設備が用意され、結果は全国集計され、大々的に発表されま
す。2025年の連邦議会選挙の際は、7000校以上が模擬選挙に参加し、200万人以上が投票に参加しまし
た。200万人以上の生徒が投票しました。まさに授業の枠を超えて、若い世代が「自分の声」を社会に届ける
感覚を体験できる、貴重な機会となっています。
ドイツの教育現場には「民主主義を維持したいなら、やるべきことはたくさんある」という共通認識があります
。「なぜナチスが生まれたのか」と歴史を振り返り、自分で考え、社会に参加し、「声」を届けられる主権者を育
もうとしています。
民主主義は、日々の中で育つ
日本では学校現場での「政治的中立」の意識が強く、「政治的な話題を避ける」傾向が長らく続いてきました
。視察に来ていた大学の先生から聞いた話によると、教師が政党名を出すことが問題視されることもあるそ
うです。
しかし、AIが生成したディープフェイク画像やフェイクニュースの拡散が問題となっている時代だからこそ、本
当に必要なのは、「偏らない」教育というよりも、「情報を疑い、自分の立場を問い、他者と対話する力」なので
はないでしょうか。
自分の声が、家族を、学校を、コミュニティーを、社会を動かすという感覚を積み上げるには、「これが好き
!」「これが嫌い」を安心して言える環境がないといけません。一つの発言に過度に責任を持たせたり、タブー
視したりして、誰かの口を塞ぐような環境は、社会にとって不健康そのもの。民主主義は、日々の行動の中に
こそ宿るものです。
「選挙って意味あるの?」「誰がやっても同じでしょ」と言われた時、皆さんならどう答えますか?
「あなたの声が社会を動かすんだよ」
と胸を張って言える社会にしたいですね。
「KonterBUNT」は、日常生活の中で差別的な発言を受けた際の対処法を、ミニゲームを通して実践的に
学べるアプリです。ゲームでは、相手を挑発するだけの反論を「悪い反論」、相手に自分の発言について再
考させる反論を「良い反論」として紹介し、戦略的な対処スキルを学べます。
性差別的な発言や、人種差別的なコメントを受けたとき、咄嗟に言葉が出てこなくてヤキモキした経験は、海
外に住んでいる人だけでなく、日本で暮らしていても皆さんにもあるはずです。
誰かに嫌なことを言われたとき、傷ついた心を守るために受け流しても、感情のまま相手にヘイトを倍返しし
ても、何も解決にはつながりません。
差別やフェイクニュースに基づくヘイトに立ち向かうには、事実に基づいた適切な反論をシミュレーションして
おくことが、民主主義の根幹を守るうえでとても重要です。
このように、ドイツでは、民主主義や選挙について学べるアプリやゲームを、教育現場でも積極的に活用し
ています。